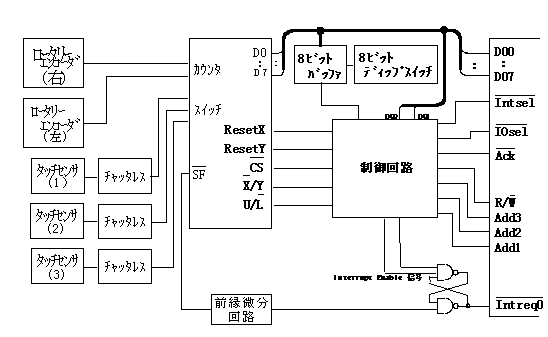
- ロータリ・エンコーダは、a、b2相入力式のものを、2個まで取り付け可能である。
- カウンタは、12ビット・バイナリ・アップ・ダウン・カウンタを用いる。
- 駆動輪が逆転の時にはカウンタはダウンカウントし、0以下になるとカウント値は2の補数表示となる。
- データ出力は、8ビットのパラレルデータを2回に分けて出力する。
- タッチセンサは、最高3個まで取付可能である。
- タッチセンサの割り込み信号は、3つのセンサの入力のORとする。
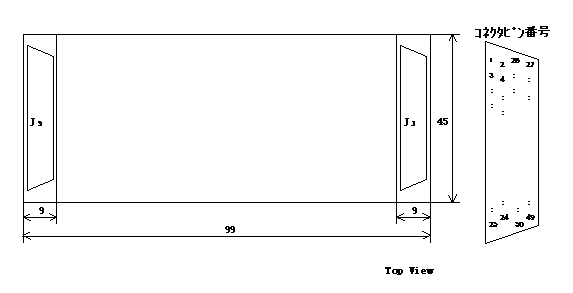
タッチセンサの信号については以下の図を参照すること。
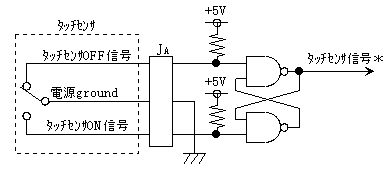
コネクタJAは、VIPC-310のコネクタで、ピンアサインは J5 と同じである。
(ii)制御フロー例
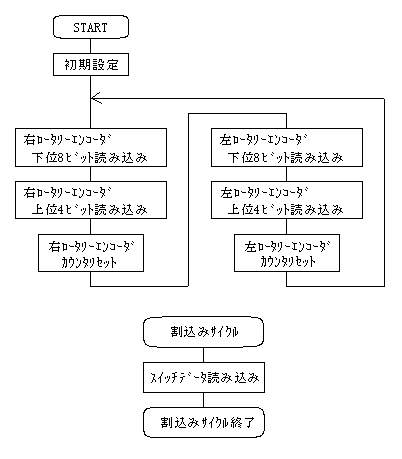
1.はじめに
ロータリエンコーダ・ボードの詳細は、次に挙げる通りである。
2.回路と使用部品について
- 2.1 カウンタ部
- カウンタ部では、ロータリエンコーダの信号処理を行う。エンコーダ用カウンタICμPD4701A(以後カウンタICと呼ぶ:NEC)を用いて、ロータリ・エンコーダの回転数をカウントする。この時、ロータリ・エンコーダの信号がカウンタICのスレッショルドレベルを満たすように抵抗値(R1〜R6)を設定する。この値は、使用するロータリ・エンコーダ毎にも変わってくるが、今回は実験によりR1、R2、R4、R5を6.2kΩ、R3、R6を220Ωとした。
- 2.2 スイッチ部
- カウンタ部に用いたカウンタICで、タッチセンサの信号処理も行う。タッチセンサには、チャッタレススイッチを用いる。チャタリング除去回路にはS-Rフリップフロップを用い、74LS279で作製する。カウンタICによりタッチセンサの状態を読み取り、スイッチフラグ(以後SF*)を発生させる。なお、このSF*を制御回路に取り込んで割込み信号を発生させる。
- 2.3 制御回路
- 制御回路部では、I/Oボードとのインタフェースを行う。その役目は、CPUからの命令の解読と、タイミングの制御、割込み信号の発生、バスリセット時のボードの初期化である。ボードは、バスリセット時にはカウンタをリセットし、タッチセンサの割り込みを禁止する。回路の小型化の為に、PLD(16V8)2個を用いて作製する。
- 2.4 割込みVECTOR発生回路
- 割込み時の割込みVECTORは、ロータリエンコーダのカウント値を出力するのと同じデータバスにのせるので、カウント値と割込みVECTORの出力の切り替えに3ステートバッファを用いる。回路は74LS244を用いて作製する。割込みVECTORの設定用に8ビットのディップスイッチを用いる。スイッチは、ロータリエンコーダ・ボードをI/Oボードに搭載したままでも操作できるように横向きのディップスイッチA6DR−8を用いる。
3.タイミングチャート
図1にカウンタリードサイクルのタイミングチャートを、図2にカウンタリセットサイクルのタイミングチャートを、図3に割込みサイクル(割込みVECTOR読込みサイクル)のタイミングチャートを、図4にバスリセット時のタイミングチャートをそれぞれ示す。なお、CLKは8MHz(T=125ns)である。
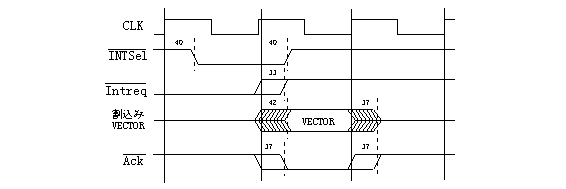
|
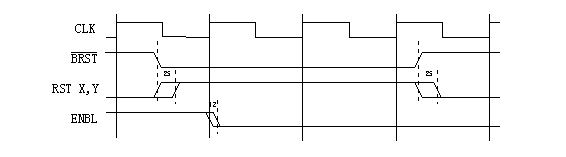
|
※ 実際はバスリセットがアクティブな状態(”L”レベル)は数百ms続く。
4.部品表
初版基板の部品表はV94−CARD−301である。
1.目的
本ドキュメントは,ロータリエンコーダボード初版(V94−PART−001,V94−PART−002,V94−CARD−x01)、及び2版(V94−PART−003,V94−PART−004,V94−CARD−x02)の使用法を明確にすることを目的とする。
2.適用範囲
本ドキュメントは,ロータリエンコーダボード初版(V94−PART−001,V94−PART−002,V94−CARD−x01)、及び2版(V94−PART−003,V94−PART−004,V94−CARD−x02)に対して適用する。
3.取付方法
1)ロータリエンコーダボードをI/Oボード(VIPC310)に載せる
ロータリエンコーダボードは、必ず IndustryPack A 側に取り付けます。
2)センサ類をI/Oボード(VIPC310)に取り付ける
ロータリエンコーダ、タッチセンサのケーブルはRE−I/Oボード接続ケーブル(V94−PART−009)を用います。ケーブルは、I/OボードのコネクタJA(IndustryPack AのI/O用のコネクタ)に、向きを確認して取り付けます。
ただし、もしもタッチセンサの取付個数が3個未満である時には、センサの取付けに加えて次の作業を行ってください。
ロータリ・エンコーダ・ボードに取り付け可能な3つのタッチセンサのうちの、取り付けないタッチセンサに対応するロータリ・エンコーダ・ボード上のジャンパを全てつなぎます。センサとジャンパの対応は、右タッチセンサがジャンパR、中央タッチセンサがジャンパM、左タッチセンサがジャンパLとなっています。図1のロータリエンコーダ・ボードの外観を参考にしてください。
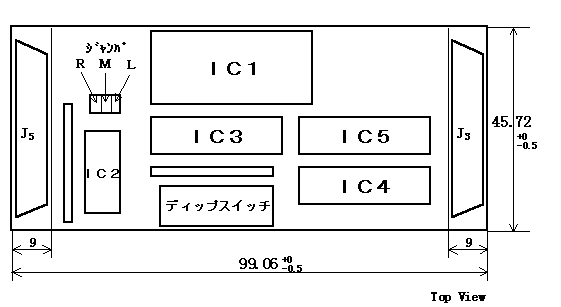
|
4.使用方法
1)はじめに
ロータリ・エンコーダ・ボードは、CPUリセットの信号で初期化されるように設計されています。初期化の内容は、次のとおりです。
- カウンタのカウント値は全て0になります
- 発生していた割込み信号は全て取り消されます
- リセット後は割込みはマスクされ、ソフトウェアによる割込みの許可を行うまでは、割込みはかかりません
2)タッチセンサを動作させる
タッチセンサを働かせるためには、次のことを行わなければなりません。
- i)タッチセンサを取り付ける
- タッチセンサは3個まで取付け可能です。ただし、取付個数が3個未満の時にはジャンパをつなぐ作業を行ってください(「3.取付方法 2)センサ類をI/Oボード(VIPC310)に取り付ける」 を参照してください)。ジャンパは、タッチセンサを取り付ける代わりにタッチセンサのOFFの状態を強制的に作り出すものなので、タッチセンサを接続したのにジャンパをつないだり、タッチセンサを接続しないところのジャンパをつなげ忘れたりといった事のないように注意してください。
- ii)VMEラックのバックプレーンの設定をする
- 割込み信号をMPUボードにつなぐため、VMEラックのバックプレーンの設定を行う。詳細は、VMEbusのマニュアルを参照する事。
- iii)VMEBus InterruptMaskResister の設定をする
- 必要な割込みレベルにあわせてInterruptMaskResisterの設定をする。タッチセンサの割込みレベルはレベル4である。設定についての詳細は、 VSBC-1 USERS MANUAL を参照する事。
- iv)割込みVectorを設定する
- 割込みVectorは、タッチセンサにより割込みが発生した時に、割込みサイクルへ移動するために必要になります。割込みVectorは、割込みサイクルに移るためのアドレスの下位8ビットになります。
割込みVectorの設定は、ロータリ・エンコーダ・ボードにあるディップスイッチで行います。ディップスイッチのSW8がアドレスA0,SW7がアドレスA1,以下SW6、SW5、SW4、SW3、SW2、SW1がそれぞれA2,A3,A4,A5,A6,A7の設定となります。また、スイッチON(=make)で論理”0”、スイッチOFF(=break)で論理”1”となります。