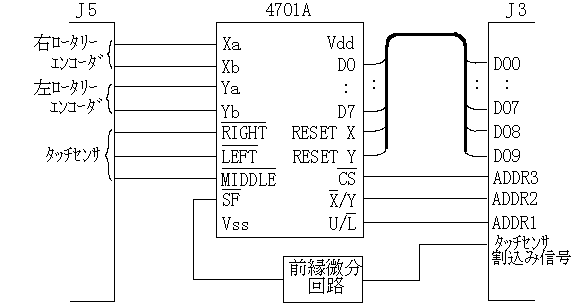
1.目的
本ドキュメントは,ロータリエンコーダボード初版(V94−PART−001,V94−PART−002,V94−CARD−*01)の作成法を明確にすることを目的とする。
2.適用範囲
本ドキュメントは,ロータリエンコーダボード初版(V94−PART−001,V94−PART−002,V94−CARD−*01)に対して適用する。
3.作成方法
以下の手順でロータリエンコーダボードを作成する。
i)基板を焼く
両面基板にパターンを焼き付け、エッチングする。パターンは、V94-CARD-401(パターンCADファイル)を用いる。エッチングが終わったら基板を正確な大きさに切る。特に基板の横幅は、いっぱいまでパターンが引かれているのでIC1及びディップスイッチのランドが削れるぐらいまで基板を削る事(図1の概観図で基板寸法を参照してください)。
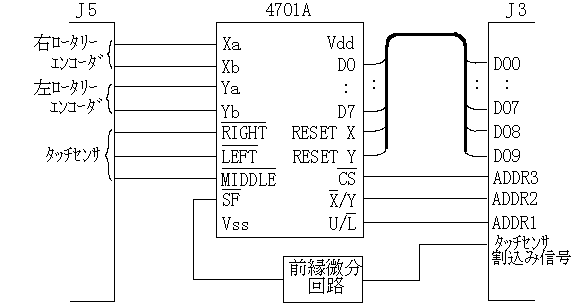
|
ii)基板に穴を開ける
ドリルは0.8mmを用いる。但し基板の四隅にある大き目のランドはIndustryPackをI/Oボードに固定する時のねじ穴であるので2.5mmのドリルで穴を開ける。
iii)半田付け
部品を基板に乗せる前に、必ず基板の表と裏(部品面と半田面)を結ぶ作業をします。基板を部品面から見た時(パターンCADファイルでの、LAYER1)に、ランドが部品の足以外の所にあるものは、全て裏側の半田面と結びます。抵抗などの足の切った残りや被服をはいだ導線などを差し込み、両面を半田付けしてください。この作業は、全部で48ヶ所あります。結びおわったら、しっかりとつながっているかどうか、導通チェックをしてください。
基板を部品面から見た時(パターンCADファイルでの、LAYER1)にランドが部品の足の所にあるもの(R4、R5、R6、C4の4パーツ、5ヶ所)は、取り付けた部品の足の部品面側も半田付けします。
残りの部品も載せて、半田付けします。但し、IC4とIC5はPLDなので、ICソケットを取り付けてください。
iv)PLDを焼く
PLDの書き込みデータは、1つのICにつき1つのディレクトリを用意してあります。必要なディレクトリは、部品表から検索してください。
ディレクトリには、テキスト形式で論理式を記したソースファイル(拡張子:PDS)と、ソースファイルから作成したドキュメントファイル(拡張子:DOC)、PLDライタ用にコンパイルしたファイル(拡張子:JED)の3つのファイルがあります。これらをフロッピーディスクに読み出しPLDライタに読み込ませてPLDの焼き付けを行ってください。
PLDを焼いたら基板に載せて完成です。
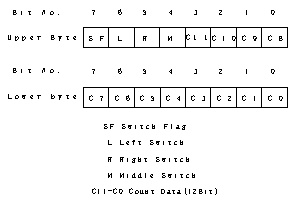
|
割込みVECTOR発生回路は、割込みサイクル時にVIPC310−IP間のデータバス(Internal Data Bus)に8ビットの割込みVECTORを載せる回路である。IPからデータバスには通常μPD4701Aの出力データが載せられる為、バス上にμPD4701Aの出力データと割込みVECTORが同時に載るようなことの無いよう、3ステートのバッファを用いて割込みVECTORの出力を制御する。割込みVECTORの設定は、8ビットディップスイッチによって行う。IPをVIPC310に搭載するとき、両者は互いにボードの部品面を向かい合わせる事になる。IPをVIPC310に搭載したまま割込みVECTORの設定を行えるよう、ディップスイッチは横向きのものを使用した。
i)物理インタフェース
IPの寸法と、コネクタピン番号を図4に示す。50ピンコネクタはAMP社の173279−3である。
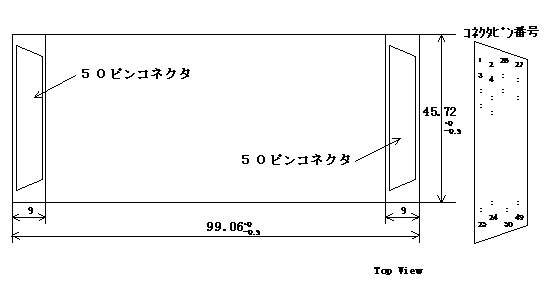
|
ii)ソフトウェアインタフェース
IPが可能なデータ入出力のサイクルには、表1に示した8種類がある。それぞれのサイクルは4つのセレクト信号(IOSel*,MemSel*,IntSel*,IDSel*)とR/W*、DMAck*により決定される。
| Cycle Type | R/W* | IOSel* | MemSel* | IntSel* | IDSel* | MDAck* |
| Input | H | L | H | H | H | H |
| Output | L | L | H | H | H | H |
| Memory Read | H | H | L | H | H | H |
| Memory Write | L | H | L | H | H | H |
| Interrupt Ack | H | H | H | L | H | H |
| ID Read | H | H | H | H | L | H |
| IO-DMA | H/L | L | H | H | H | L |
| Memory-DMA | H/L | H | L | H | H | L |
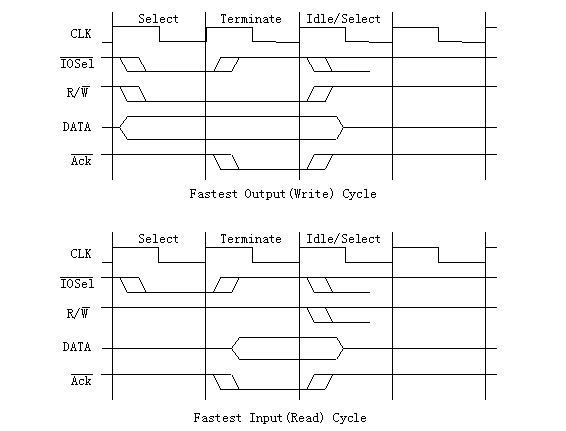
|
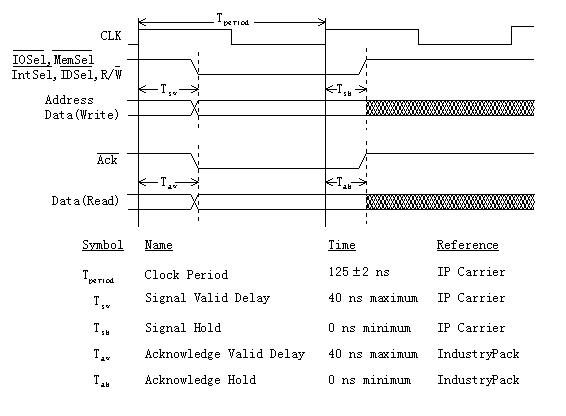
|
制御回路は、以上のような仕様を満たすように設計しなければならない。
制御回路では、セレクト信号、アドレス、データなどをデコードしてCPUからの命令を解読し、CLKと同期を取り、ロータリエンコーダ信号処理回路やタッチセンサ信号処理回路に必要な信号を送ったり、命令に応じたデータをCPU側に返したりする。IPの大きさを考慮して、回路をPLDで作製することにした。
| No. | 信号名 | 方向 | 内容 | 備考 |
| 1 | GND | -- | GND | |
| 2 | CLK | ← | Clock 8MHz | |
| 3 | BRESET* | ← | CPUリセット信号 | |
| 4 | D00 | ←→ | DATA 20 | |
| 5 | D01 | ←→ | DATA 21 | |
| 6 | D02 | ←→ | DATA 22 | |
| 7 | D03 | ←→ | DATA 23 | |
| 8 | D04 | ←→ | DATA 24 | |
| 9 | D05 | ←→ | DATA 25 | |
| 10 | D06 | ←→ | DATA 26 | |
| 11 | D07 | ←→ | DATA 27 | |
| 12 | D08 | ←→ | DATA 28 | 未使用 |
| 13 | D09 | ←→ | DATA 29 | 未使用 |
| 14 | D10 | ←→ | DATA 210 | 未使用 |
| 15 | D11 | ←→ | DATA 211 | 未使用 |
| 16 | D12 | ←→ | DATA 212 | 未使用 |
| 17 | D13 | ←→ | DATA 213 | 未使用 |
| 18 | D14 | ←→ | DATA 214 | 未使用 |
| 19 | D15 | ←→ | DATA 215 | 未使用 |
| 20 | BS0* | ← | Byte Select (下位ÊÞ²Ä) | BS0*=0 (active) |
| 21 | BS1* | ← | Byte Select (上位ÊÞ²Ä) | BS1*=1 (negative) |
| 22 | V- | -- | 電源-12V | 未使用 |
| 23 | V+ | -- | 電源+12V | 未使用 |
| 24 | Vcc | -- | 電源+5V | |
| 25 | GND | -- | GND | |
| 26 | GND | -- | GND | |
| 27 | Vcc | -- | 電源+5V | |
| 28 | PWR* | ← | Read*Write Select | 1=Read,0=Write |
| 29 | IDA* | ← | ID PROM Select 信号 | |
| 30 | H1 | ← | high level 入力 | |
| 31 | MEMSELA* | ← | Memory R*W Cycle 信号 | 未使用 |
| 32 | H2 | ← | high level 入力 | |
| 33 | INTSELA* | ← | Interrupt Cycle 信号 | |
| 34 | H3 | ← | high level 入力 | |
| 35 | IOSELA* | ← | I/O Cycle 信号 | |
| 36 | H4 | ← | high level 入力 | |
| 37 | ADDR1 | ← | Address 21 | |
| 38 | H5 | ← | high level 入力 | |
| 39 | ADDR2 | ← | Address 22 | |
| 40 | H6 | ← | high level 入力 | |
| 41 | ADDR3 | ← | Address 23 | |
| 42 | IRQA0* | → | Interrupt 信号 (割込み level=4) | |
| 43 | ADDR4 | ← | Address 24 | |
| 44 | IRQA1* | → | Interrupt 信号 (割込み level=5) | 未使用 |
| 45 | ADDR5 | ← | Address 25 | |
| 46 | H7 | ← | high level 入力 | |
| 47 | ADDR6 | ← | Address 26 | |
| 48 | ACKA* | → | Acknowledge | |
| 49 | +5PSTBT | -- | VIPC310ボードのÊÞ¯ÃØ°電源 | ÃÞ°À保存用¤未使用 |
| 50 | GND | -- | GND |
| No. | 信号名 | 方向 | 内容 | 備考 |
| 1 | GND | -- | GND | |
| 2 | GND | -- | GND | |
| 3 | GND | -- | GND | |
| 4 | GND | -- | GND | |
| 5 | GND | -- | GND | |
| 6 | GND | -- | GND | |
| 7 | GND | -- | GND | |
| 8 | GND | -- | GND | |
| 9 | GND | -- | GND | |
| 10 | GND | -- | GND | |
| 11 | GND | -- | GND | |
| 12 | GND | -- | GND | |
| 13 | GND | -- | GND | |
| 14 | GND | -- | GND | |
| 15 | GND | -- | GND | |
| 16 | GND | -- | GND | |
| 17 | GND | -- | GND | |
| 18 | GND | -- | GND | |
| 19 | GND | -- | GND | |
| 20 | GND | -- | GND | |
| 21 | GND | -- | GND | |
| 22 | GND | -- | GND | |
| 23 | GND | -- | GND | |
| 24 | GND | -- | GND | |
| 25 | GND | -- | GND | |
| 26 | GND | -- | GND | |
| 27 | RRa | ← | 右ロータリ・エンコーダa相信号 | |
| 28 | GND | -- | GND | |
| 29 | Vcc | -- | 電源+5V | |
| 30 | GND | -- | GND | |
| 31 | RRb | ← | 右ロータリ・エンコーダb相信号 | |
| 32 | GND | -- | GND | |
| 33 | RLa | ← | 左ロータリ・エンコーダa相信号 | |
| 34 | GND | -- | GND | |
| 35 | Vcc | -- | 電源+5V | |
| 36 | GND | -- | GND | |
| 37 | RLb | ← | 左ロータリ・エンコーダb相信号 | |
| 38 | GND | -- | GND | |
| 39 | TRs* | ← | 右タッチセンサON信号 | |
| 40 | GND | -- | GND | |
| 41 | TRr* | ← | 右タッチセンサOFF信号 | |
| 42 | GND | -- | GND | |
| 43 | TMs* | ← | 中央タッチセンサON信号 | |
| 44 | GND | -- | GND | |
| 45 | TMr* | ← | 中央タッチセンサOFF信号 | |
| 46 | GND | -- | GND | |
| 47 | TLs* | ← | 左タッチセンサON信号 | |
| 48 | GND | -- | GND | |
| 49 | TLr* | ← | 左タッチセンサOFF信号 | |
| 50 | GND | -- | GND |