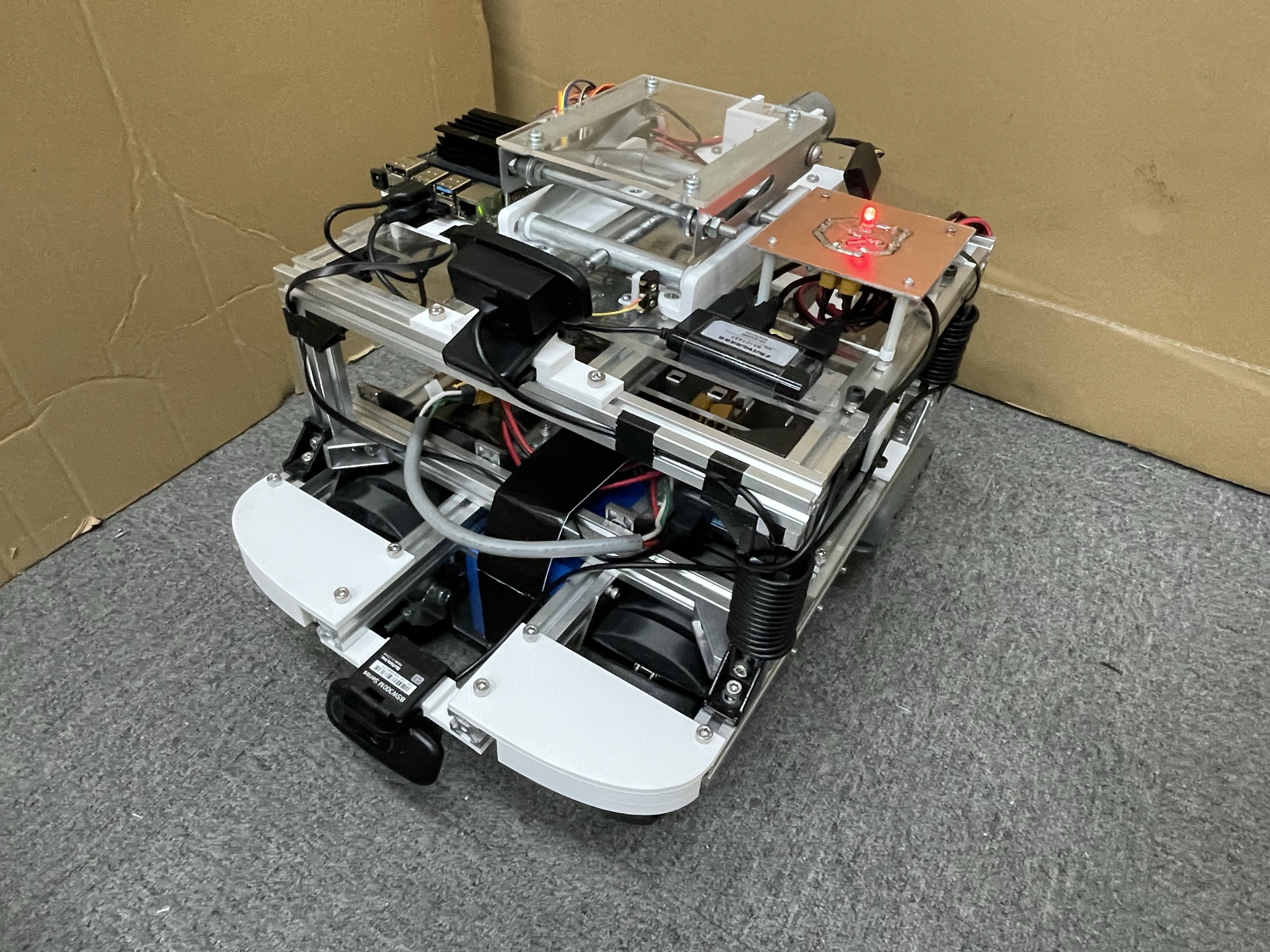
fig.1 華蟻 全体

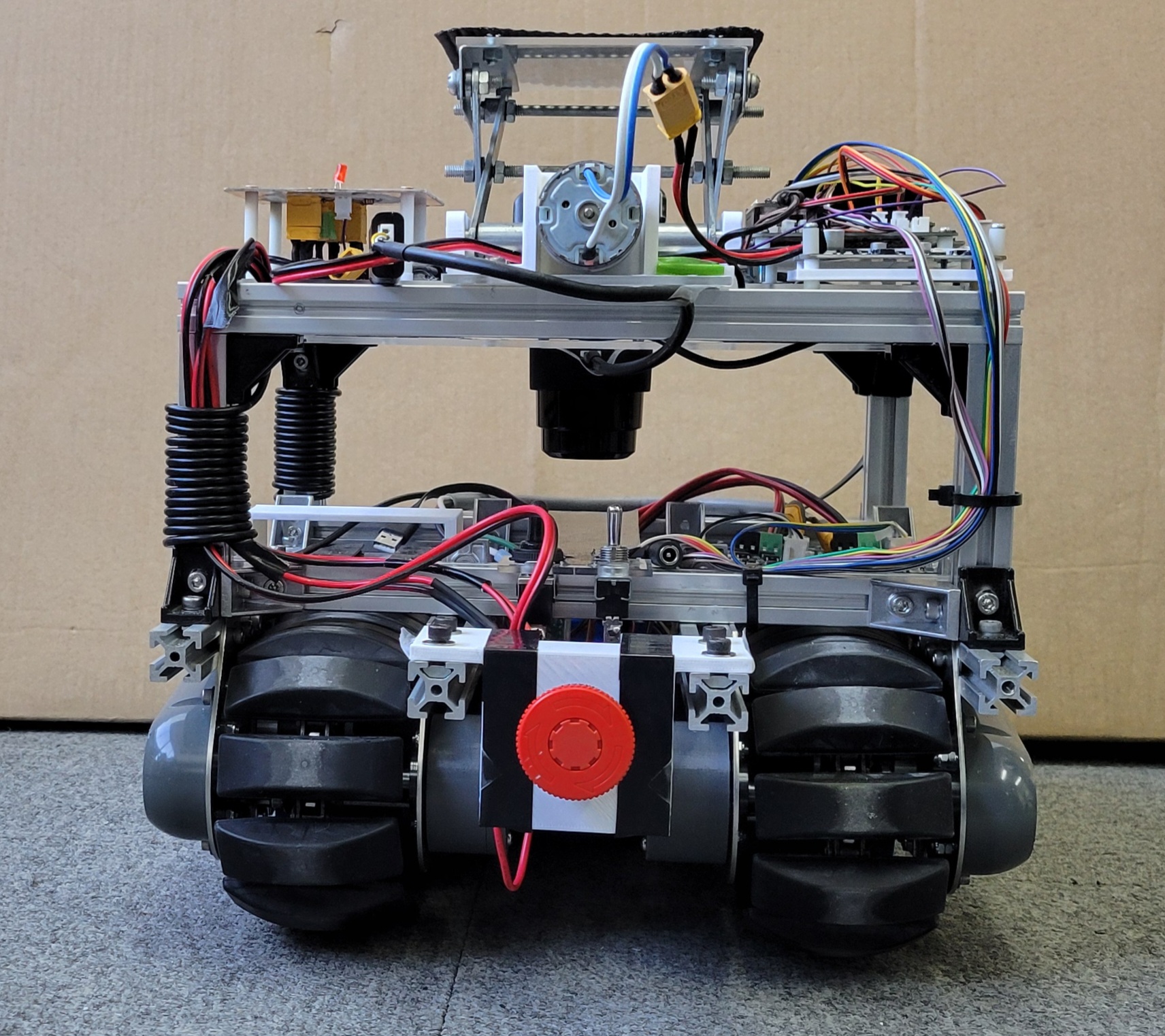
fig.2 華蟻 正面と背面
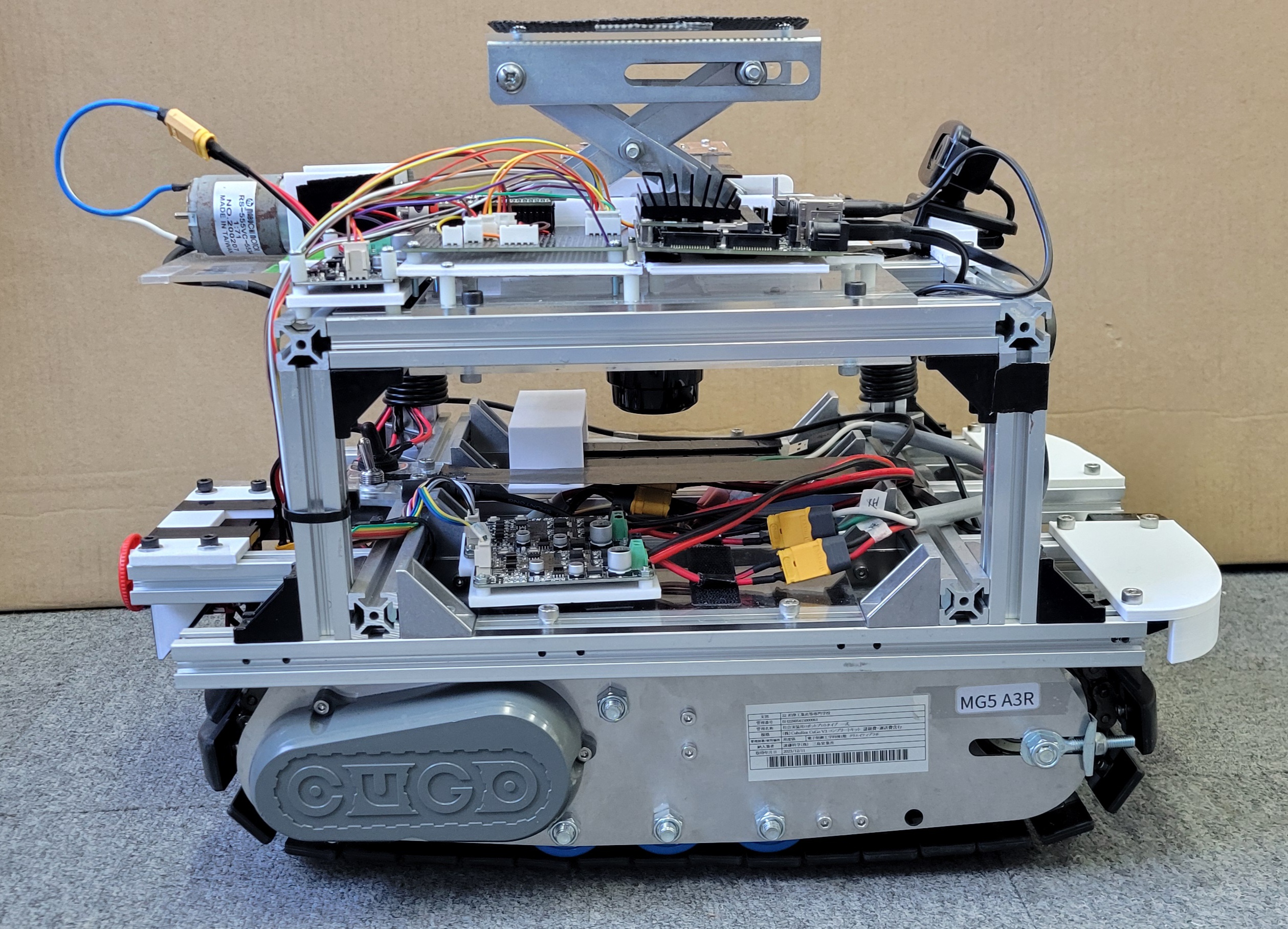
fig.3 華蟻 側面

fig.4 華蟻 上面
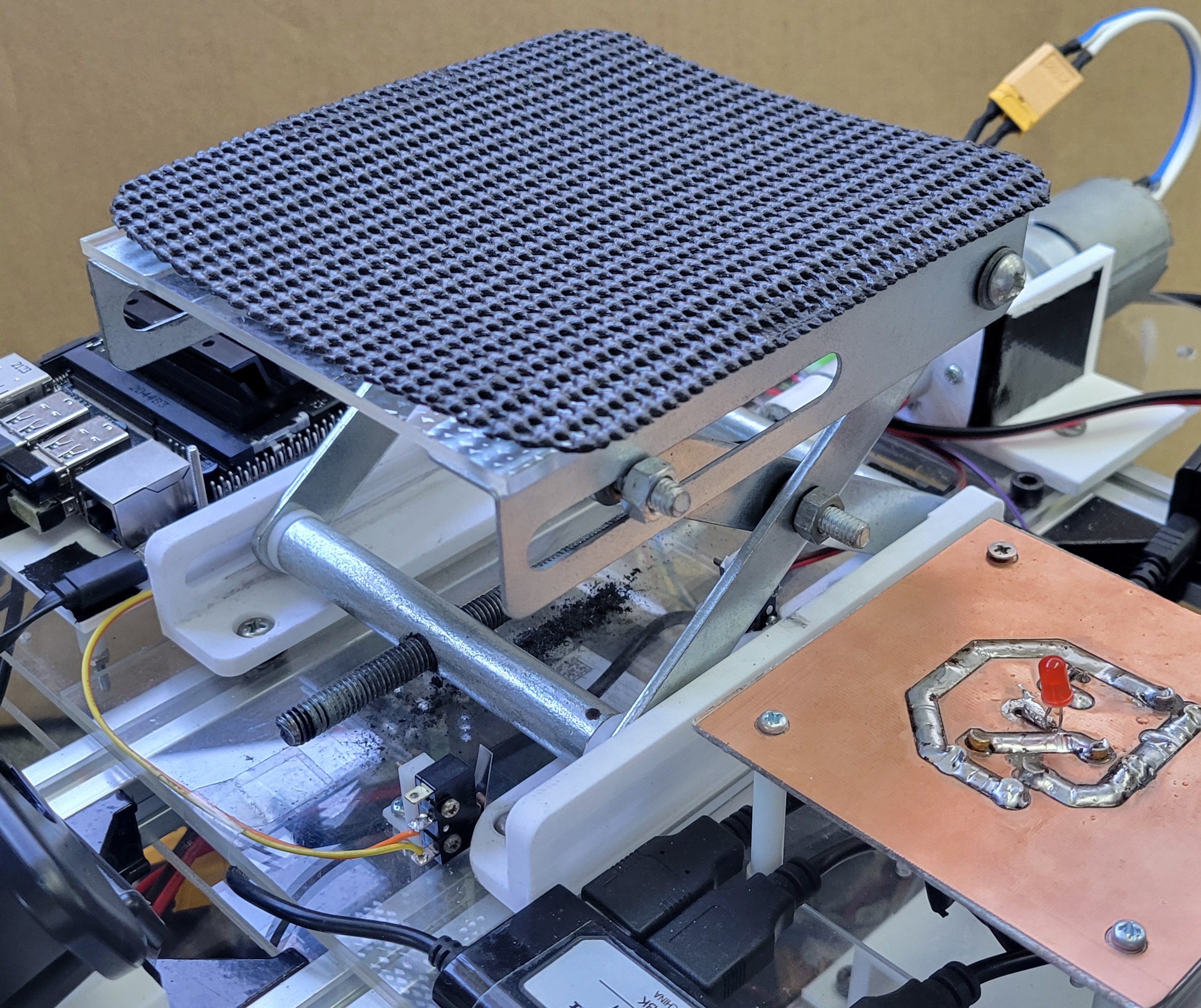
fig.5 華蟻_ジャッキ
| 名称 | MIRS2403 メカニクス詳細設計書 開発報告書 |
|---|---|
| 番号 | MIRS2403-MECH-0005 |
| 版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
|---|---|---|---|---|
| A01 | 2025.02.03 | 稲志展,小林孝博 | 青木 | 第一版 |
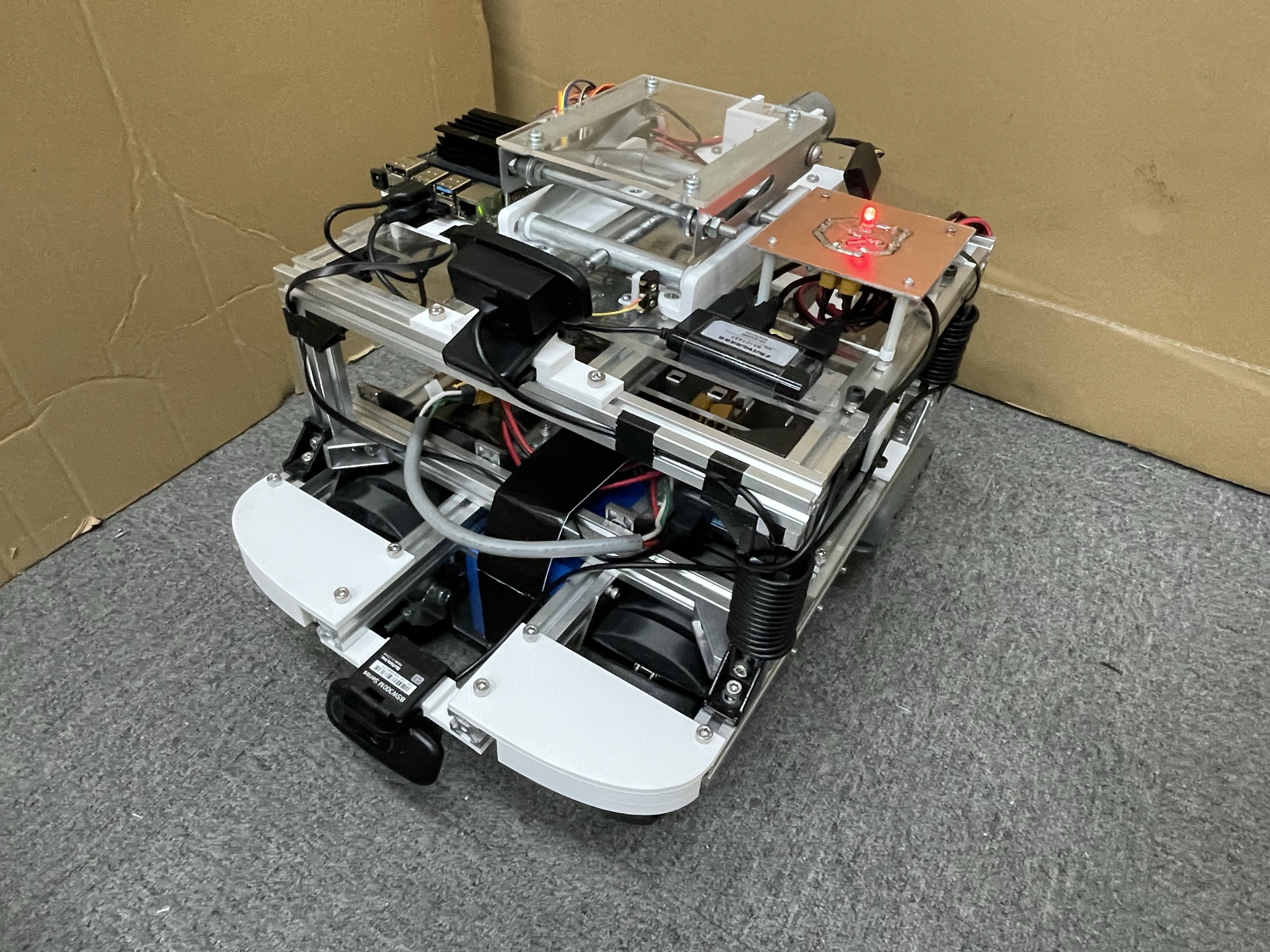

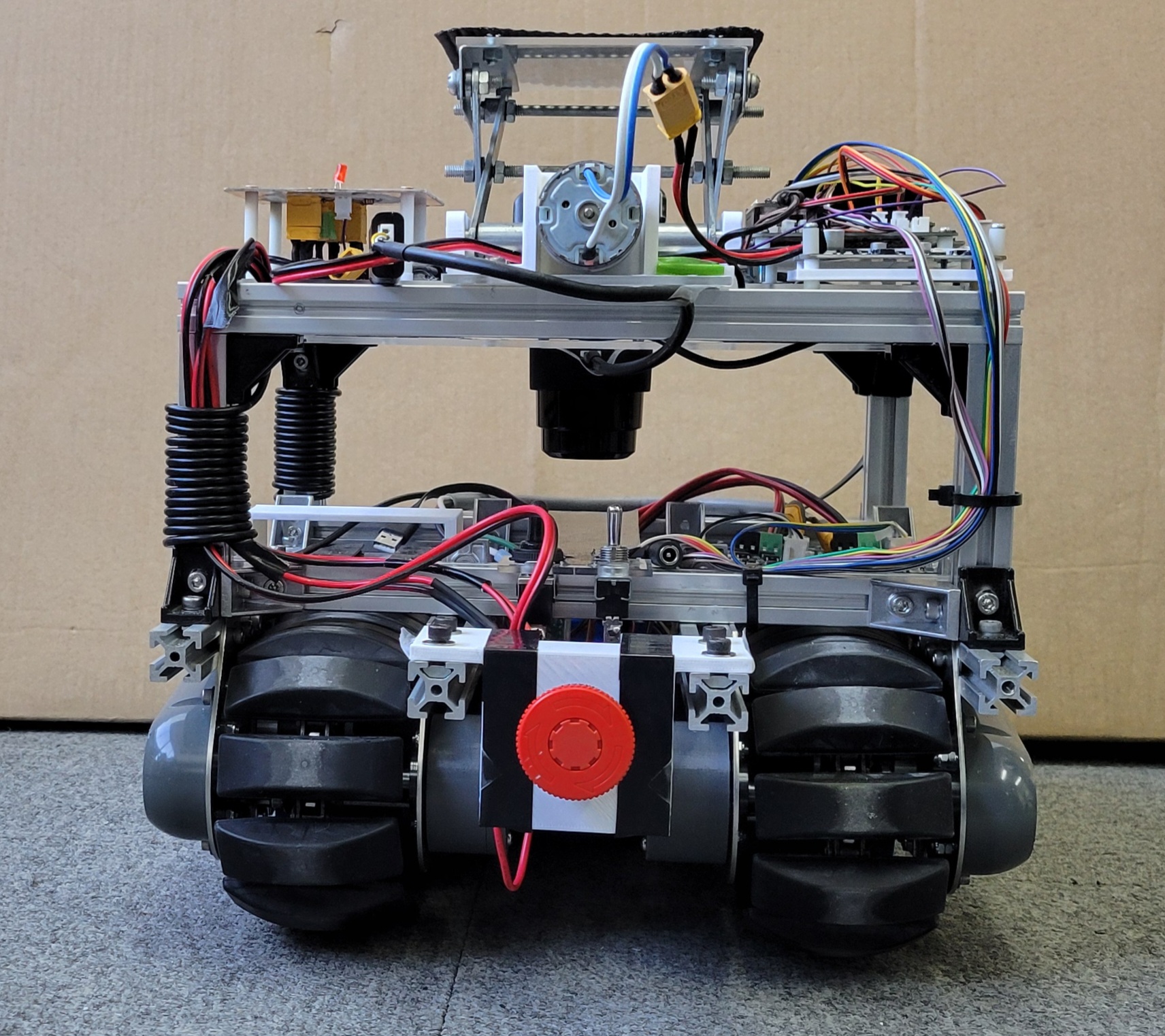
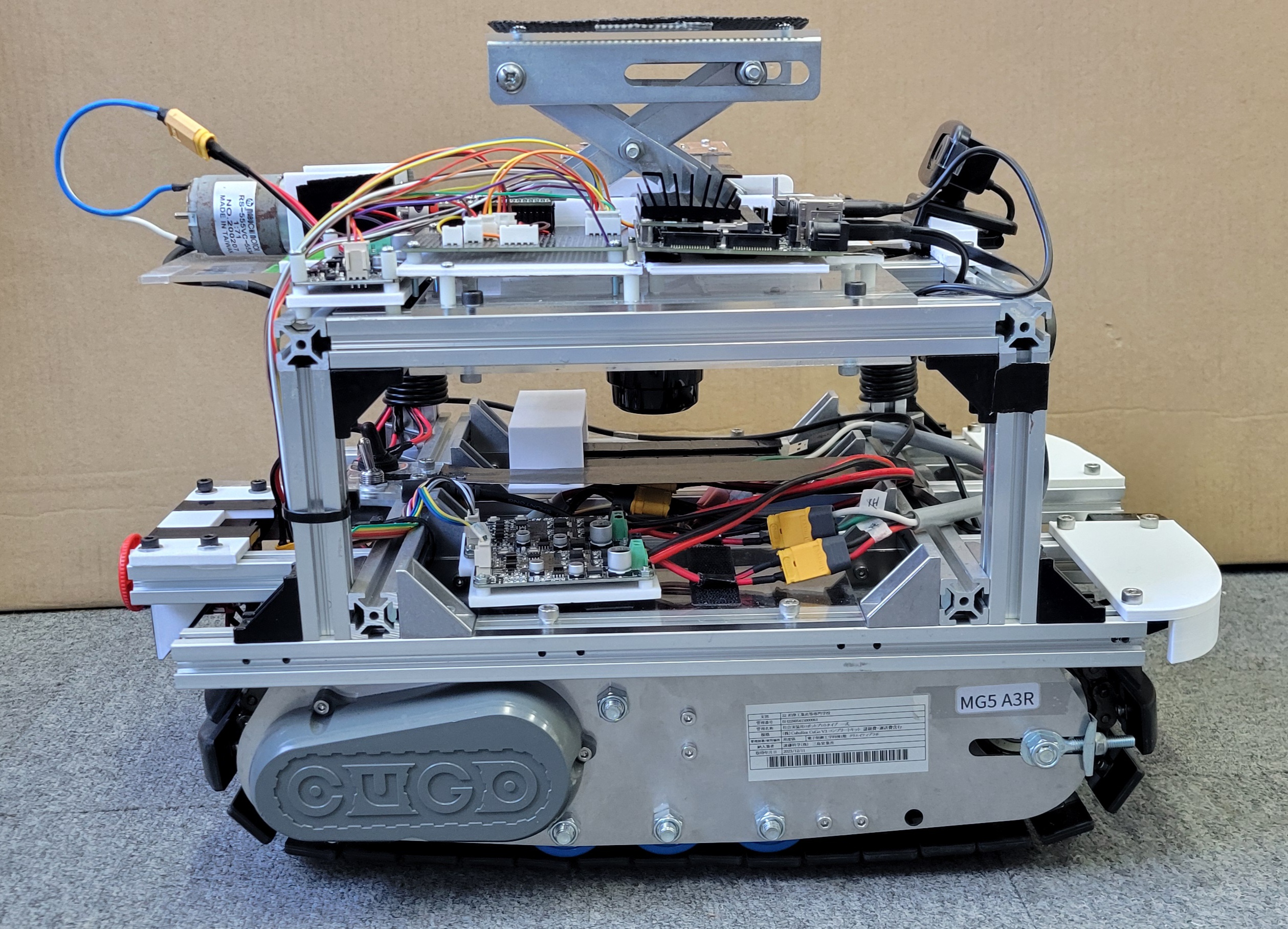

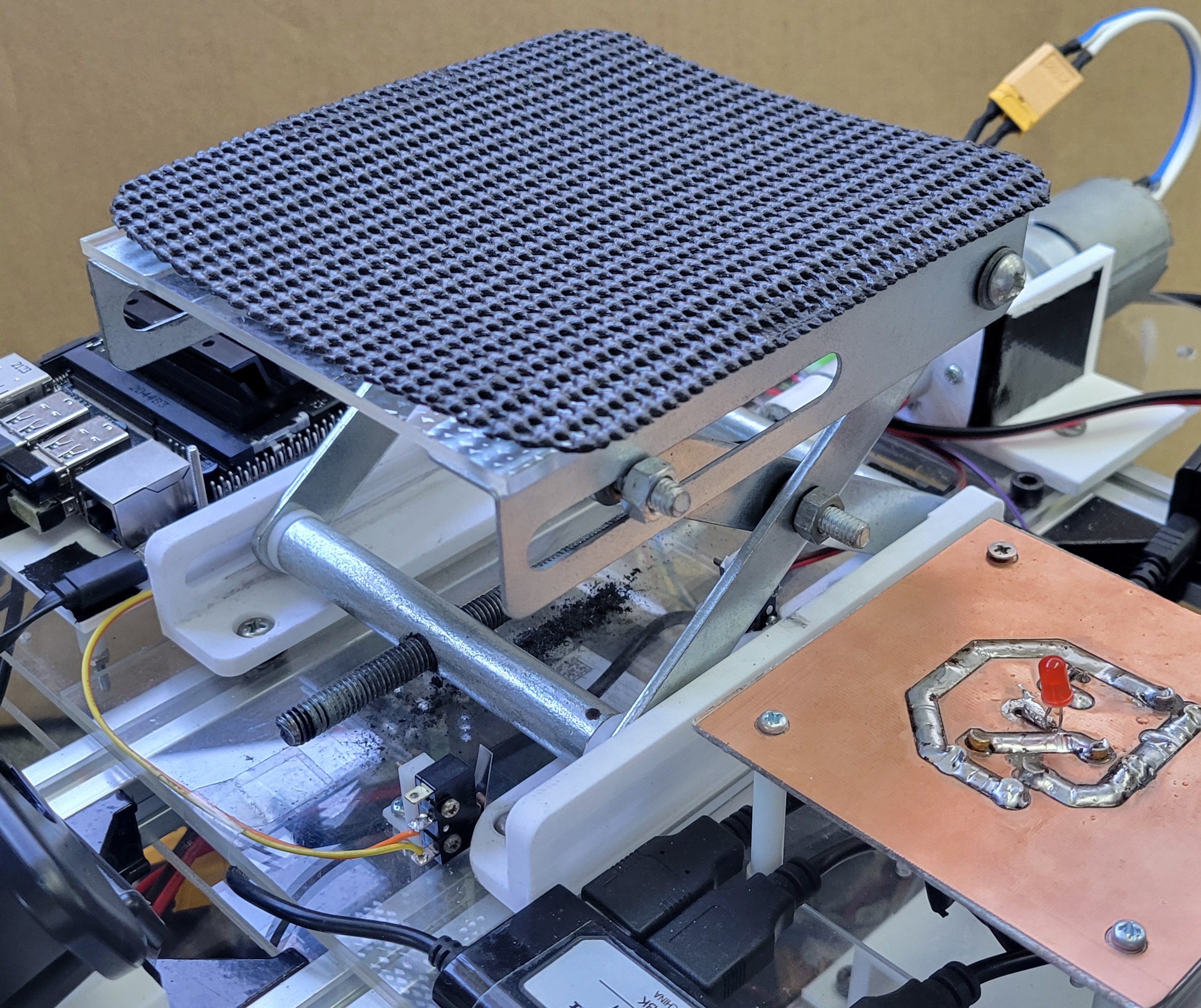
| 大きさ | 単位 | |
|---|---|---|
| 華蟻前後幅 | 520 | mm |
| 華蟻横幅 | 325 |
mm |
| 最高(最低) | 410(350) |
mm |
| 重量 | 19.5 |
kg |