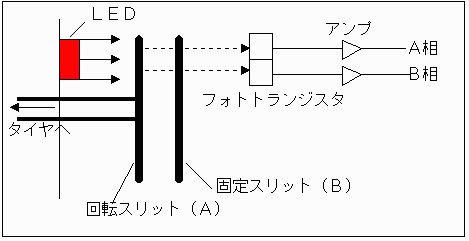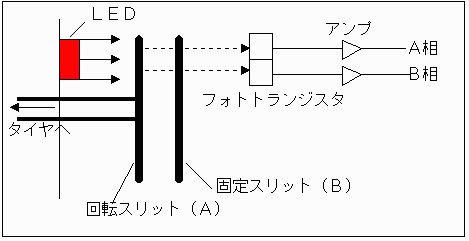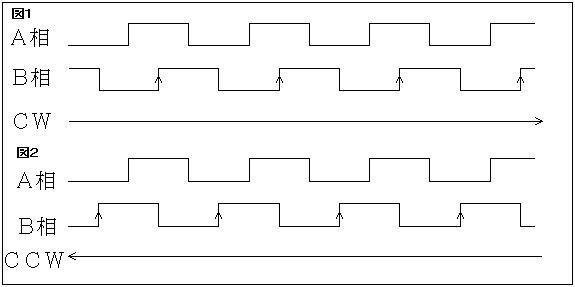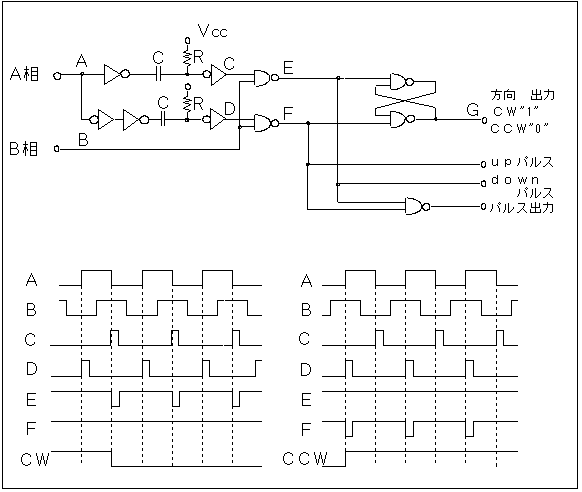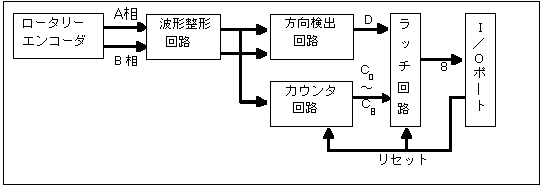encoder
ロータリーエンコーダの調査研究
3番 安部 和洋
1.ロータリーエンコーダとは
ロータリーエンコーダは、タイヤの回転量をパルス数に変換する機能を持つ。その変換方式には光電式、ブラシ式、磁気式などがあるが、MIRSでは、最も一般的な光電式を用いる。
また出力パルスの形式により、インクリメント型(変位のみの情報を出力)とアブソリュウト型(絶対位置を出力)の2つに大きく分けられるが、ここでは、安価で構造も小さいインクリメント型を使用する。
2.機能性能
このボードは、ロータリ・エンコーダからの信号を取り込み、カウンタでカウントし、CPUの要求に応じてカウント値を出力するものである。また、タッチセンサの信号を取り込みスイッチの状態を調べ、スイッチ割込みの割込み信号を発生させるのも、このボードである。
3.光電式ロータリーエンコーダの概要
(1)回転量の検出
回転軸に取り付けられた回転スリット(A)と固定スリット(B)を挟んで発光ダイオード(LED)と受光素子(フォトトランジスタ)が取り付けられてあり、回転スリット(A)が回転すると、ダイオードの光がスリットによって通過・遮断する。この光を受光素子で検出し、信号(パルス)に変換して回転したか否か判断する。出力信号を2相にするため、固定スリット(B)はスリットが2つに分かれていて、それぞれ90度位相がずれている。
ロータリーエンコーダからの出力信号は近似正弦波形であるので、これを波形整形回路でパルス波形にへんかんする。
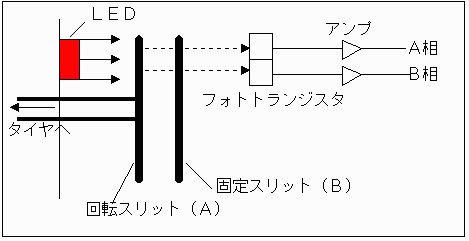
(2)回転方向(正転・逆転)の判別
ロータリーエンコーダからの出力信号は、波形整形回路によりパルス信号A、Bに変換されその組み合わせは、回転方向により2つのパターンになる。
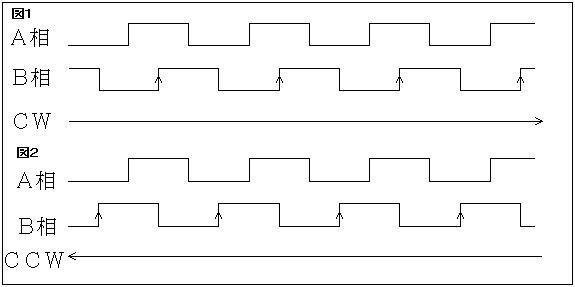
図のようにパルス信号A、Bは90度位相がずれているが、回転方向によってずれ方が異なる。これを利用して回転方向を検出する。
図1(正転)の場合、B信号の立ち上がり時にA信号は必ず”H”になっているため、方向検出信号は方向検出回路により”H”になる。
図2(逆転)の場合、B信号の立ち上がり時にA信号は必ず”L”になっているため、方向検出信号は方向検出回路により”L”になる。
(3)回転速度の検出
A、B信号の周波数と回転数は比例しているから、そのパルスを一定時間間隔にカウントし回転数をもとめれば、回転速度を検出できる。
(4)パルス弁別回路
2相パルス出力型のエンコーダ正転、逆転を検出するために必要な回路。通常、このA、B相の動きよりup/downパルスを作りだし、必要桁数のup/downカウンタに入力し、カウンタの内容を読み取る事で回転量を知る事が出来る。パルス弁別回路は、このup/downパルスを作り出す回路である。
下にパルス弁別回路を示す。
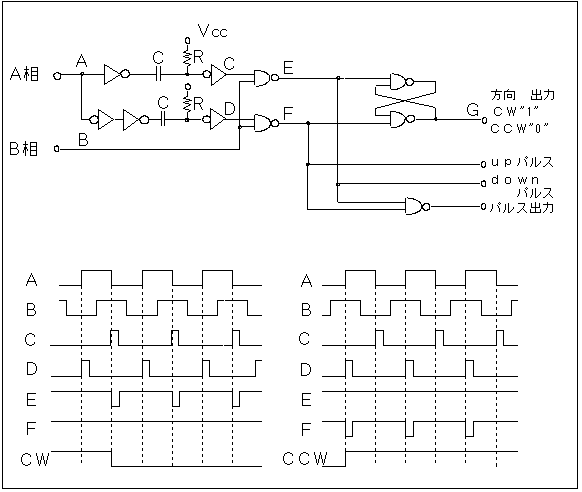
4.信号処理のブロック
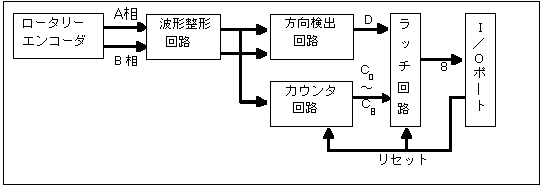
(1)波形整形回路
ロータリーエンコーダからの出力信号は近似正弦波形なので、これをパルス波形に変換する。OPアンプをコンパレータとして使用し、スレッショルド電圧によりHレベルとLレベルに分けられる。また、HからLとLからHの場合のスレッショルド電圧の違いを利用すれば、多少のノイズにも耐えられる。
(2)方向検出回路
波形整形回路から出力された信号A,信号Bはそれぞれ90度位相がずれている。正転の場合は信号Aが信号Bに対して位相が進み、逆転の場合は信号Aが遅れる。ここでは、この位相差を利用して方向を検出する。
正転の場合、信号Bが立ち上がるとき、信号AはHレベルであり、逆転の場合、信号AはLレベルである。信号Aのエッジ検出と信号Bの論理積で方向検出回路は作られる。
(3)カウンタ回路
パルス信号Aをカウントする。I/Oポートは8ビットあるが、1ビットを回転方向を示すのに使うので残る7ビットを使いカウンタを作る。なお、リセット信号によってリセットされる
(4)ラッチ回路
I/Oで値を引き渡す場合には一定時間、値を変化させないようにする必要がある。しかし、カウンタを止めてしまうと値が不正確になるため、ラッチを利用する。リセット信号の立ち上がりでラッチする。
目次に戻る
参考文献
mirs9404/memo/encode.sam
mirs9501/kihon/chousa/enco.sam
Last Update : 1997.1.23
Dep. of Electoronics and Control Enginnering