4.光電式ロータリエンコーダの概要
- (1)回転量の検出
2枚のスリット円盤A,Bを挟んで発光ダイオード(LED)と受光素子(フォトトランジスタ)が相対して置いてあり、回転スリット(A)が回転する事により、LEDの光が透過/遮断する。この光を受光素子で検出することで回転したか否か判断する。出力信号を2相にするため、固定スリット(B)はスリットが2つに分かれている。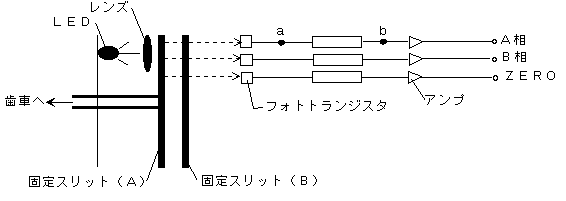
各端子における波形の例を左に示した。aでは不定形な波形が、bでは定形なパルスに、更にアンプを通して+5Vになる。ZERO相はエンコーダ1回転につき1パルス。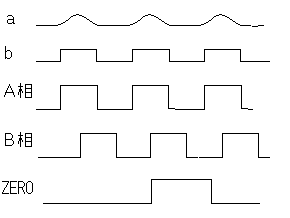
- (2)波形整形回路
ロータリエンコーダからの出力信号(A相、B相)は近似正弦波形であるので、これをパルス波形(Ap、Bp)に変換する。OPアンプをコンパレータとして使用し、スレッショルド電圧によりHレベルとLレベルに分けられる。また、HLとL→Hの場合のスレッショルド電圧の違いを利用すれば、多少のノイズにも耐えられる。
- (3)方向検出回路
波形整形回路から出力されたAp,Bpはそれぞれ90度位相がずれている。正転の場合はApがBpに対して位相が進み、逆転の場合はApが遅れる。ここでは、この位相差を利用して方向を検出する。
正転の場合、Bpが立ち上がるとき、ApはHレベルであり、逆転の場合、ApはLレベルである。Apのエッジ検出とBpの論理積で方向検出回路は作られる。
- (4)カウンタ回路
パルスApをカウントするI/Oポートは8ビットあるが、回転方向を示すのに1ビット使うので残る7ビットを使用する。実現を容易にするため16進カウンタを2個つなげた256進カウンタを使用し、その最上位ビットは使用しないものとする。
- (5)ラッチ回路
I/Oポートで値を引き渡す場合には一定時間、値を変化させないようにする必要がある。しかし、カウンタを止めてしまうと値が不正確になるため、ラッチを利用する。リセット信号の立ち上がりでラッチする。
- (6)マルチプレクサ
左右のデータを読み分けるために使う。左右独立して使用すれば必要ではないが、ポート数が不足する場合必要である。セレクト用に1ビット増えるが、データのビット数は半分になり、結果として使用ビット数は7ビット減る。