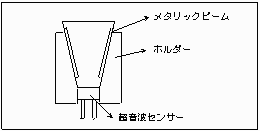 |
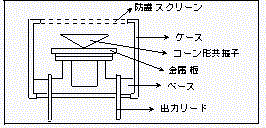 |
- 3. 超音波センサーの構成
-
超音波センサーは、下図のような構成になっている。反射波は物体の形によりエコーして残るが、反射波の先頭だけを検出して、最も近い所からの反射時間をはかる。下図では発振器を使用しているが発振波形でなく一発の高圧パルスで超音波スピーカを駆動することもある。
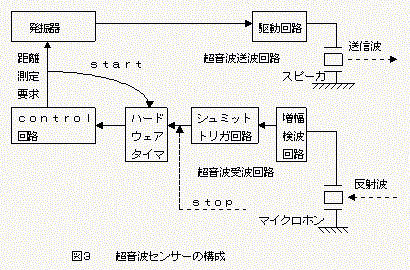
- 3.超音波センサーの計測方法
超音波センサの計測方法としては、代表的なものに次の方法がある。
1、連続波信号レベル検知方法
2、パルス波反射時間計測方法
1は回路構成は簡単だが、あまり長い距離が計測できない。
2は送信信号を発射し受信信号が返ってくるまでの時間tを計測し、物体との距離をL、音速をCとして次のような式で距離を計算する。
L=C×t÷2
MIRSの競技場は2m四方で30cm幅の進入禁止区域があるので左図から約2mまで検出できればよい。従って、
L=2[m]、C=344[m/s]
(音速)とすれば最大時間Tmaxは、
Tmax = 2×2÷344 = 0.11[s] = 10[ms]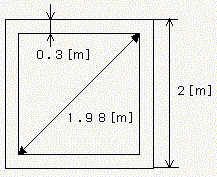
超音波が物体に当たって反射する条件を求める。
周波数がf=40[kHz]、音速がv=344[m/sec]とすると
v=fλより
λ=344÷(40×103)[m]=8.6[mm]
となる。
従って波長が8.6[mm]なので、壁の凹凸が8.6[mm]以下の場合に鏡となる。
fig.1の場合は、反射波はR(受信器)に返ってこない。
fig.2の場合は、反射波が受信されそれに要した時間Tから距離Lが求まる。fig.1 fig.2 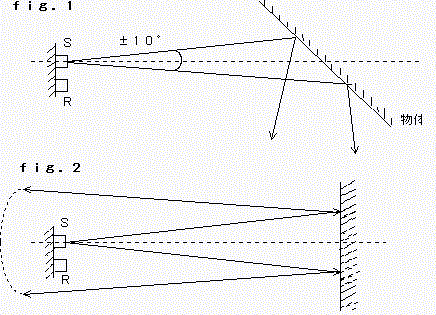
- 4.超音波センサの固定方法
A.超音波センサの送信部及び受信部はその最大計測距離が2.8m、最小計距離が0.1m以内となるように固定する。但し固定角の微調整可能な機構を設ける。(下図参照)
B.3組の超音波センサの固定精度はfig.3を満足するものとする。
C.超音波センサ間の相互干渉、受信部で超音波の直接回り込み波を受信するのを防ぐために送信部をスポンジ製ホーン等で覆う。fig.3 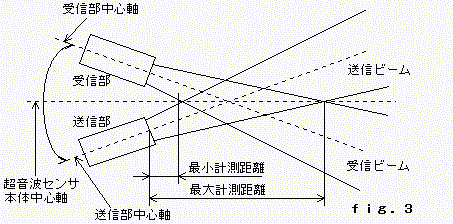
- 5.超音波スピーカと超音波マイクロホン
電機信号を超音波に変えて空気中に発射する超音波スピーカ(送波器)と、空気中を進んできた超音波を受けてそれを電気信号に変える超音波マイクロホン(受波器)を合わせて超音波トランスジューサと言う。
音は空気の振動であるから超音波トランスジューサは電機信号を機械的振動に変えたりその逆の役割を果たす。
これらの電気一振動変換素子は、原理的には一つの素子が送信器にも受波器にも働くが、送波と受波では空気の振動振幅も大幅に異なり、しかもインピーダンスを変えたほうが効率が良いので個々のトランスジューサを利用するのが普通である。
超音波を発生するための送信回路にはCMOSゲート回路による発振器や、マイクロコンピュータのクロック信号を分周する回路によってトランスジューサの共振周波数のパルス列を作り、これにより超音波トランスジューサを駆動させる方式を取る。
fig.4はこの例でマイクロコンピュータからのコントロール信号が「H」の間だけ発振が起こり超音波が送波される。fig.4 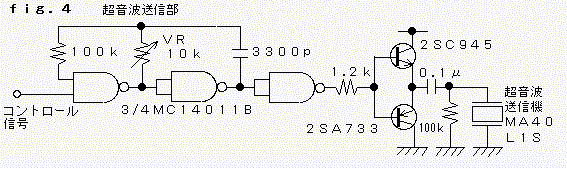
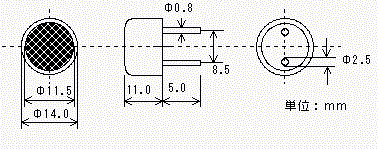
- 6.超音波センサーの指向性と反射性
指向性とは音が横に広がらないで目的の方向にすべての音エネルギが1本のビームとなって直進する度合である。
超音波はトランスジューサから一定の広がりを持ってビーム状に発射される。そのビームの波形を、超音波トランスジューサの指向性という。
市販されている超音波トランスジューサの指向性は、それ程鋭くなく半値角として±20°〜30°程度の広がりを持つ。 超音波センサの指向性が広いと、センサによって計測された対称物の形はかなりぼけたものになる。(fig.5参照)
すなわち、超音波センサは距離方向の分解能の精度は高いが、横方向の分解能の精度はそれ程高くないのである。そのためこの指向性を改善する方法として、トランスジューサにホーンアンテナを取り付けるという手段がある。
アンテナには一般に指向性を鋭くすると同時に、中心方向の利得を稼ぐという利点がある。但しホーンアンテナの設計を理論的に行うことは難しいので、ある程度の試行検討によりホーンの形を決める必要がある。
fig.6に円錐形のホーンアンテナの一例を示す。fig.5 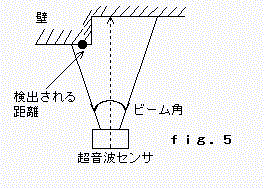
fig.6 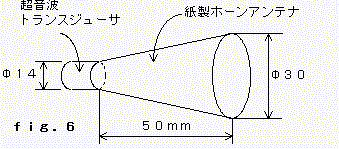
超音波のような波が対象物に当たった場合、対象物表面に凹凸があればそこで 散乱しあらゆる方向から反射散乱波が観測される。しかし、もし対照物に凹凸が なければ散乱しないで入射角=反射角で反射するだけとなり、反射散乱波は検出されない。
波にとって対象物が凹凸であるかどうかは、その表面の粗さと波長の関係で決まる。
競技場の壁は数十kHzの超音波にとってほとんど平らになるので超音波センサでは斜めから壁を見た場合、通常その壁は検出できない。故に壁と垂直に近い場合のみ反射波が検出できることになる。
また、この指向性をεとすると次のようになる。
ε = c/λ(この値が大きいほど指向性が良いことになる)・・・ (2.1)
λ = c/f ・・・(2.2)
λ : 波長 (長さの単位で10−6m)
c : 音の速さ(m/s)
f : 周波数(Hz)
D : 音源の直径(mm)
従って2.1式より指向性を高めるには周波数の高いものが良いことになる。精度を必要とする通信用(測定)は指向性を高めるため高周波超音波の周波数を1ー10MHz(メガ 106)のものを使用する。
特殊なものは30ー50MHz級のものも使用する場合がある。
この利点は指向性の良い送信器をそのまま受信器に使用する、横から伝播して周波雑音をすべて除外できる。
- 7.ハードウェアタイマ
超音波センサでは、要した時間を距離に換算する必要がある。そこでソフトウェアタイマで時間を換算することを考えると、CPUは換算中ほかの処理ができないという欠点がある。一方、ハードウェアタイマを用いれば、その間もほかの処理を行なうことが出来る。
従って、本MIRSではハードウェアタイマを使用することにする。
ハードウェアタイマとしてはそれぞれのCPUに周辺LSIとして準備されてい る タイマ用ICを使うと簡単である。クロック発生回路とマイコンから読むことの出来るカウンタ回路を構成すればそれで十分なハードウェアタイマとなる。
ハードウェアタイマの1例をfig.7に示す。fig.7 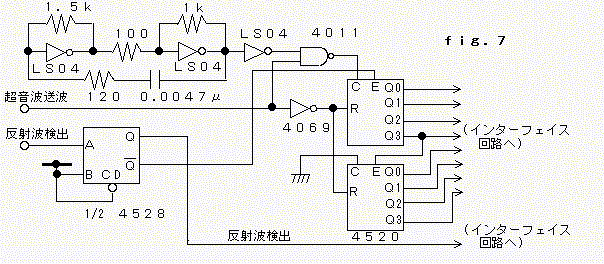
- 8.超音波センサ使用上の注意
- 壁に対して斜めに入射した超音波はほとんど戻ってこない。
- 超音波トランスジューサは、周波数選択性が著しいので、送信回路に発振機を用いる時は周波数調整を線密に行なうことや、経時変化や温度変化による発振機のドリフト(注1)にも注意が必要である。
- 受波器は、マイクロホンであるから、外部の音システム自体の機械的振動で誤動作する恐れがあるので、受波器はゴムなどを用いて機械的振動が伝わらないように取り付ける必要がある。(fig.8)
- 受波増幅機は、大きな増幅率をかせぐアナログ回路であり、回路の雑音に注意しなければならない。
- 続けて距離を測定する場合は、以前に発射した超音波に対する反射や残響が十分に減衰するまでの時間(数[ms])をおいてから次の超音波を発射するようにする。
fig.8 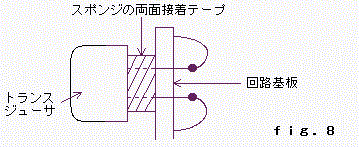
(注1) ドリフト−−−直接結合増幅回路は、直流信号まで増幅できる。それゆえ、温度や電源電圧の変化によってIcobやVbeが変化して、コレクタ電流が変化した場合、これと信号直流分は分別できない。入力変動に原因せずに、このように電流が変動する現象をドリフトと呼んでいる。
参照・・・mirs9403の中のcyuonpa1.sam- 壁に対して斜めに入射した超音波はほとんど戻ってこない。
目次に戻る