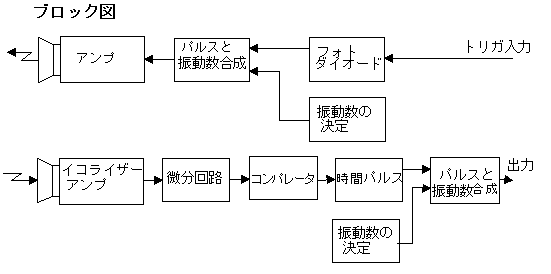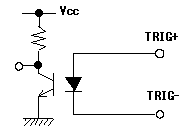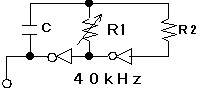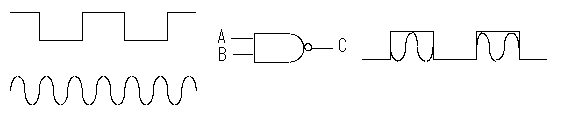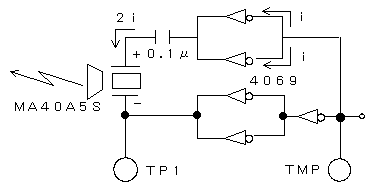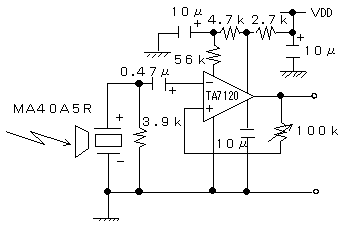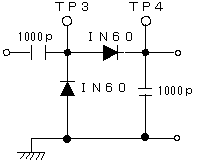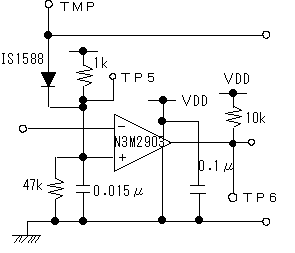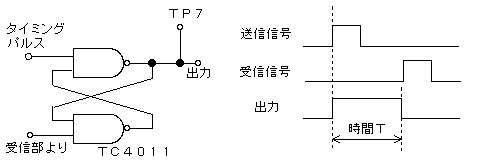1.カウンタ回路の検討
- カウントの手段
カウントはPCが出力する周期20[ms]でパルス幅4[ms]のパルス信号をトリガとしてカウントを開始する。当然、受信信号が16[ms]以上のものは受信できない。従って、測定は16[ms]で打ち切ることになる。測定を16[ms]で打ち切っても音速は346[m/s]だから、超音波は5.5[m]進み、測定は、帰ってきた反射波であるので5.5/2=2.75[m]まで測定できる。これは競技場内の最大の長さを上回っているので大丈夫である。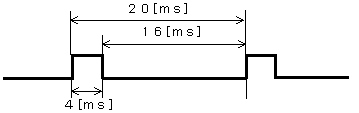
- (2) カウンタの選定
- 超音波の波長は8.6[mm]であるから約1[cm]の精度以上での測定は不可能である。また、超音波の速度は34600[cm/s]でるから、1[cm]を進むのに約30[μs]かかる。よって超音波測定は超音波が行って帰ってきたものを検出するものであるので1[cm]の測定をするのにカウンタは1カウント2[cm]であればよい。従って測定パルスは60[μs]の周期にする。また、測定時間は16[ms]で打ち切るので、
16[ms]/60[μs]=266.6<267[カウント]
従って267カウント前後のカウンタを必要とすることが分かる。8bitカウンタは256カウントであるのでこれとほぼ同数である。
よって、8bitカウンタを使用することにする。